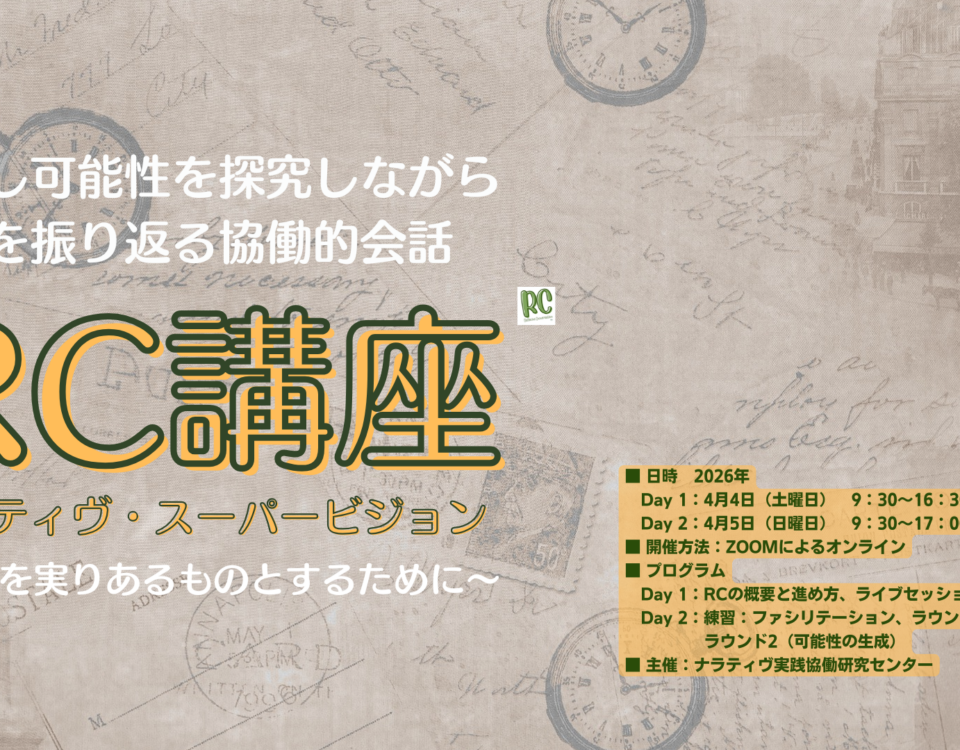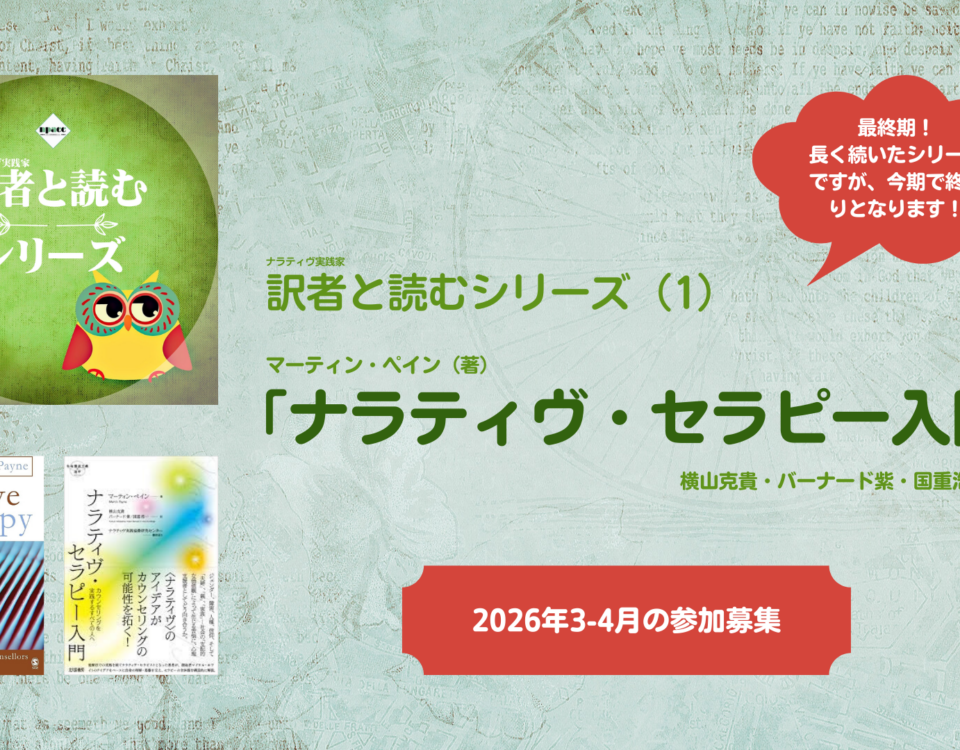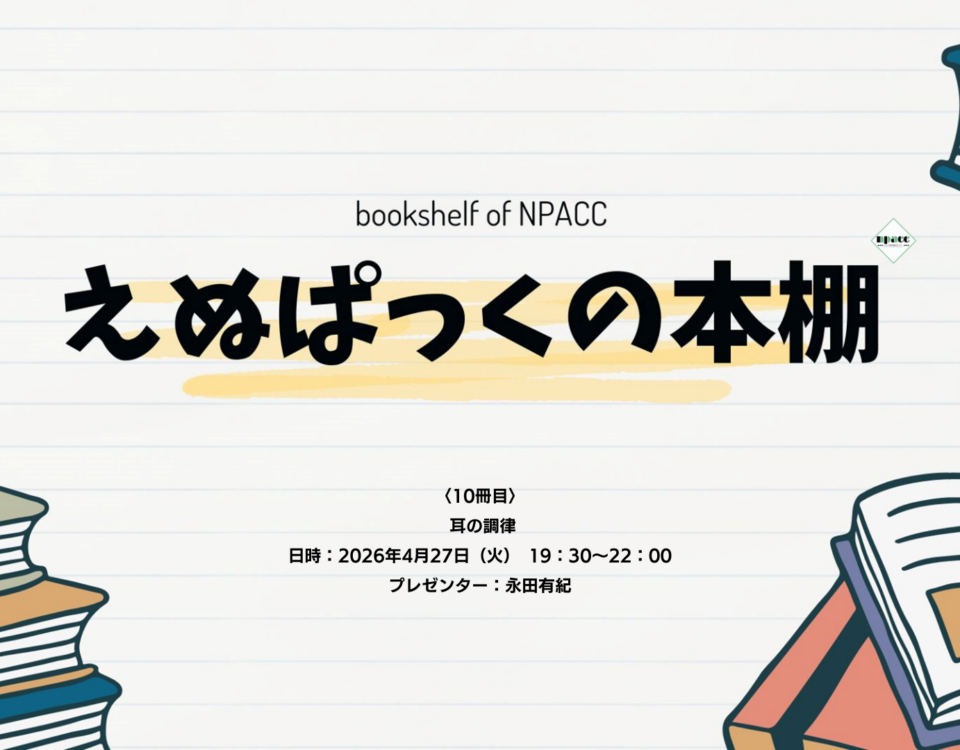えぬぱっく・ライブラリ
2025-06-14
ナラティヴ・セラピー・ワークショップ・ミニシリーズ(京都)2025(参加者の声を掲載)
2025-07-26「ナラティヴ・カーニバル 2025」のプログラムに参加した感想を頂いています。その中で、ホームページに掲載していいという許可を頂いたものだけを以下に掲載いたします。
なお、ナラティヴ・カーニバル 2025のイベントページはこちらになります。
https://npacc.jp/narrativecarnival2025/
| プログラム 1-1:臨床家のリフレクション(藤田悠紀子さん編) |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 藤田さんの人生のストーリーをお聞きし、心理士という専門職であっても、とても多くの悩みや思いがあって、そのようなことを持っているからこそ、相談に来られる方の思いを大切にしたカウンセリングをされてきたのだと感じました。「相談者が障害に適応するためのカウンセリングではなく、どうなりたいか?どう生きた?を一緒に考えていく」そんな関りをされてきたというお話をお聴き出来たことはとても学びになりました。ありがとうございました。 |
| 幼少期からのお話を聴かせていただき、まるで導かれたように臨床心理士として活動されたのだなと感じました。「本当のことをしたい」とおっしゃられたこととがとても印象に残りました。これを藤田さんは心の叫びとおっしゃっていました。表現の仕方は変われどきっと誰しもが持つ心の叫びなのではないかと思いました。対人支援・援助をする際にその人の「本当のこと」って何だろうか、それを見つけられるような対話を大切にしたいと考えました。 |
| ・参加してよかったです。 ・考えたこと 藤田さんの問いへの対応を見て、これまでの自身の問いへの対応が、表面的であったように感じました。問いに対して嘘ではない自身の気持ちを応えているが、自身に向けられた問いに対し、問いを丁寧に自身に向け、自身の深いところに問いを当て、応えることも自身には必要であることを感じました。 ・これからの取り組み 地元での学びの場への取り組み これまでよりも地元での学びの場の必要性を感じていましたが、本日の話を伺う中で改めて学びの場づくりへの思いが高まりました。そして、ただ皆で学ぶでなく、良いと感じる人から学ぶ機会を作ることへの思いも高まりました。まずは、学びの場を作りたいと思っていことを発すること始めていこうと思います。 |
| 自分の事のようだった。忖度なく医師に意見して議論したほうが、わかりあえて組織全体が良い方向へ変化していくのだということだと思う。遠慮して引きこもっていてはだめだと再認識できた。 |
| 初めて藤田さんのお話を伺いました。お話の途中であった平木先生からこうさんへの流れがとても興味深かったです。 藤田さんの今までの活動や関わりの大きさには全く及びませんが、『自分が何になりたいか』そこを考えていく機会が最近頻出していて、少しヒントになるようなものを受け取れたような気持ちになっています。 そして一番のギフトは『こどもはよくわかっている』 小さい頃何度、大人の話に加わるなと叱られたことでしょう。こどもはこどもなりの意見を持っていると信じていたので、極力自分のこどもには遮ることのないようにしてきたつもりです。もちろん、相手に確認はしていないのでどう感じているかは不明ですが、逆に、娘との二人暮らし故に負担を与えていた事が多かったかもしれません。 時折、あの時はこんな思いだったを振り返れるこども時代があることは、理不尽さもあるけれど、違いを知る意味ではよかったと思えることでもあるのかもしれません。 このような考えをいただけたこの時間はかけがえのない時間で、とても有意義でした。 (使用可能な箇所があれば、抜粋での掲載はお任せいたします。よろしくお願いいたします) |
| 藤田さんの心理職としての歴史、一人の人としての歴史、両方について厚みのあるお話をうかがうことができて、50代の心理士で女性である私もとても揺さぶられました。「閉じていた」藤田さんが病院の先生たちとの出会いなどから「言いたいことを言っていいんだ」「自分のことを言っていいんだ」と感じ、行動するようになっていく旅路をお聴きしながら、そのような「声を出していく」プロセスを藤田さん自身が経ていることが、藤田さんの臨床に生かされていることを感じました。(若い頃にも、実は声を出すことにつながるようなエピソードもあったと思いながら、聞いていましたけれども。) またご自身が不調になったことがあることも、(私自身が不調を経験し、年齢を実感していることも重なりますが)藤田さんの「普通の人」としての実践につながっていると思いました。今年齢からくる身体的な変化を実感し、支援する側としてだけでなく、「支援を受け入れたい」と考えていらっしゃることも、専門家の立場から降りて「人」としての支援を追求する現役の臨床家としての藤田さんの人生に大きな影響がありそうですが、変化を楽しんでいらっしゃる軽やかさを感じました。 最後に、今後の自分自身の取り組みに大きな影響を与えそうなこととして印象に残ったことですが、最初に配属された職場で仕事に就いた時、「そこに置かれた」と感じたとおっしゃっていたことや「継続していくことの大切さ」も、ちょうど昨今の私が感じていたことと重なります。自分は普通の人で大した人ではないといつも思っているのですが、今の立場や環境に置かれた自分に何ができるのか、私なりに考え、役割を果たしたいと思っています。藤田さんの人生の話を聴く機会をいただき、ありがとうございました。 |
| 藤田さんが歩んでこられた物語を聴かせていただけたこと、とても心が満たされました。行きづまっていたと感じておられた藤田さんに「こういう考え方もあるのよ」とナラティヴのことを話された平木先生の働きかけも心に響きました。少し先を歩いてくださっていた先輩の存在がわたしたちがいる現在地に大きな貢献をしてくださったことに感謝の気持ちがうまれました。 |
| 藤田さんが、幼い時から現在に至る自分に起きていたこと、その影響を語り、自分が求めていることを問い続け来たプロセスをお聞きしました。問い続けるまっすぐさ、力を感じました。現在一定の到達を得て、そしてまた、これからやりたいこと、やれそうなことへ動き始めていることもお聞きしました。「本当に自分のやりたいこと」という言葉が残っています。自分への問いかけになっていくようです。 |
| 発表者の人生の物語を通じて、自分の言葉を発し、好奇心を持って知識を深め、さらにその過程を振り返り続けることの大切さについて改めて考えさせられました。そのように取り組み続けていくことで、クライエントさん自身が本当に必要としているものや、それに対する自分の取り組みについての理解が深まっていくのだと思いました。 |
| 藤田さんの語りを聞いて、ナラティブで言われる「なんとか言葉にしてみる」が腑に落ちてきました。その人の中にある情景、感情を表現するとき、言葉が先か、その人が先か、のようなことがあるのだなと受け取りました。自分に触れながら言葉にすること、言葉に自分を追い越させないことに取り組んでみたいと思いました。 |
| 藤田さんのこれまでの今までと今とこれからを聞かせていただく事て、勇気づけられました。何をしてよいかわからないところから、学びの場を立ち上げられたことや、これからやろうとされていることを聞かせていただき、私も頑張ろうという思いが強くなりました。また臨床家としての姿勢で「その人がどうなりたいか、どう望んでいるかを支援する」という姿勢は見習いたいと思いました。 |
| 藤田さんのお話を聞くことができたのは、本当に得難い体験でした。これまでも、そしてこれからも、その生き方、有り様に心を揺さぶられます。企画していただきありがとうございました。 |
| 藤田さんの言葉のなかで「どうすることが支援だと思っているか、カウンセラーが明確にすることが大事だ」ということが強く残っています。自分が支援しているなかで、相手を環境に適応させることを周囲の人に求められているように勝手に思っているなぁと感じ、けっして適応させることが支援ではないということを再び強く確認することができました。 カウンセリングの場で、前に座った人には関わることが許される、という感覚は自分にもあるなぁと感じられたので、そういうことを意識できたことで、また一つ考えていく材料を授けてもらった思いです。 自分も場が与えられたら、まだまだやっていけるぞという希望もいただきました。 ありがとうございました。 |
| 大切なお話を聴かせていただき、ありがとうございました。人生の映画を一本観させていただいたような時間でした。 いままでの道のりをそこにあったこと、そこにいた人の話としてそのままにお話下さることがとても印象的でした。それは、お母さんとの関係性や大人たちの話から聞こえてくる違和感と「本当のことがしたい」という感覚など、それらのことをなかったこととせず、そこにあるものとして持ち続け、考え続け、感じ続け、見続けたからこそなのではないだろうかと思ったりしています。 「就職後の不安は奇妙になかった」という言葉もとても印象に残っています。言いたいことを声にしてみることや様々な行動に起こす原動力は、子供のころから持たれていたという「本当のことがしたい」という感覚とつながっていたりするのでしょうか。機会があれば、ぜひお伺いしてみたいと思ったりしました。 |
| 貴重なお話を伺えて、大変深い学びになりました。家の都合でところどころ聞けなかったのですが、臨床家としての真摯で謙虚な姿勢に心を動かされました。正確な表現は失念してしまいましたが、クライエントさんに対する「問題を、私が触れてよい状態の方が、ここに来てくださった」最後の「やっと普通の人になれた」という言葉が、心に残りました。 |
| 臨床家として真っすぐに「本当」のクライアント支援を追求して生きてこられた藤田さんの言葉には全く自己満足や衒いのようなものがなく、ドクターなどとのバトルも、その純粋で妥協のない「真の支援とはな何か」の追求ゆえに相手や周囲の心を打つものがあったのだろうと思いました。そして、それが図らずも藤田さんご自身の「本当のことをしたい」「本当の自分を生きたい」という自己探求、自己実現と重なり合いながらなされてきたように感じました。 幼少期からご自身の僅かな表現やその存在自体さえもお母様おばあ様に逐一影響を及ぼすことを敏感に感受して、周囲とコミュニケーションがうまくとれなかったという藤田さんが、臨床家となってバトルとなるほどはっきりと信念を主張されるようになったこと。CLと関わることを通して人と関わることが本当に自分がしたかったことだと覚られたこと。今は自ら人との豊かなコミュニケーションの中に生きていらっしゃるわけですね。お聞きしていて、その様変わりに驚かされました。がんじがらめのしがらみ、孤独から抜け出し、青空に向かって強く自由には羽ばたいていくものの姿を感じました。翼は上空を目指しながらもその目は地上での閉ざされた物語を忘れてはいない。だからこそ一層今の大空の広さ高さが心にしみるのではないか。藤田さんの2つの物語は繋がっていると感じ、抑圧された時代があったからこそ、本当の自分とは何かを求め続け、出会えたのではないか。そんなことも思いました。本当のご自身を生きられてきた藤田さんは周囲を強く引きつけ、いつの間にか孤独とは縁のない人になっていることも、参加された方々の最後のコメントに感じました。 今の人生はきっと藤田さんの天命に合っているから「できる限りは続けていきたい」とシンプルな言葉になるのでしょう。理由はおっしゃいませんでしたが、資格の更新をやめらたことにも生き方が表れているように思えました。そこに突っ張り感はなく、「肩書がないと困っている。でもなんとかなっている」とおっしゃったことにお人柄を感じ、囚われない生き方が伝わってきました。 内省しながら、吟味しながら、本当の言葉で語ってくださった藤田さんの時間は清々しく、心打たれるものがあり、また人として勇気づけられた気がします。 お会いできたことを感謝しております。 素晴らしいプログラムでした。 |
| 「相手が生きていくことの手伝いは、自分が生きていくことの手伝いでもあった。」という言葉が強く残っています。「言いたいことを言っていい」本音を言える場があることの大切さを、あらためて確認しました。 |
| 非常に深く、考えさせられる貴重なお話を伺えたと思います。来歴も非常に印象深かったのですが、特に「本当のことをしたい」、そしてその代償行動として問題行動を起こされていたというお話が、支援のあり方の中で話されていた、「クライエントを社会に適応させることだけが支援だとは思っていない。適応させることはその人が本当に望んでいることではない、だから症状・問題として出している。それはどういうことかを考えながら対話していく」ということと深く結びついていたと感じました。また、「表現としては同じ言葉だが、その裏には特有の経験・体験がある、そこをちゃんと理解しようと努力することなしにわかった気になってしまう」という言葉がひびきました。私自身は支援の専門家ではありませんが、対話のあり方に対してとても大きな示唆をいただけたと思います。 |
| 臨床家としての藤田さんが語られたご自身のお話に感銘を受けました。支援者の方の物語にふれる機会はなかなかありません。今回藤田さんの子どもの頃からの背景や仕事をされていく中での思いにふれることで、誠実に自分の人生を歩んでこれれた方を知ることができました。この機会に少しずつ自分のこれまでを振り返ってみたいと思います。そして一人一人のその人の物語を聞ける自分になりたいと感じました。今後も臨床家のリフレクションの機会がありましたらうれしいです。大切なお話をありがとうございました。 |
| プログラム 1-2:話し手とふりかえるオープンダイアローグ 〜リフレクティングの練習の仕方について〜 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| オープンダイアローグをもっと勉強しようと思いました |
| ODの振り返り~自分自身のリフレクティングを振り返る、それを話し手に聞いてもらって返してもらう振り返りの振り返りという構造が新鮮でした。振り返りのポイントが明示されていることが良かったと思います。 |
| 話し手の言葉をそのまま拾ったり、印象に残った言葉や感じたことをそのまま話した体験が、とても貴重でした。日々の会話でも意識したいと思いました。 |
| リフレクティングの練習に取り入れたいと思った。振り返りのふりかえりがあることが、不安を薄くすると思った。 |
| 話し手をさせて頂きましたが 内容がセンシティブという事で聞いていい話しなのかというリフレクティングが返って来た時に 精神科によって人生滅茶苦茶に破壊されてしまって 人生被害を受けてしまった私にとっては 非日常の日々が日常で普通の事なので それが辛過ぎるのですが 何を話しても良いと言いながらも 私にとって普通はセンシティブなのかと辛くなってしまいました また 私もつい頑張っている方のお話しをお聞きしていて つい褒めてしまいがちですが 認証と称賛は難しいと思いました |
| プログラム 1-3:劇団CNP第2 回公演「ルワンダ パンデミックにおけるロックダウン中の希望とローカルな知識の放送」 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| このような機会がなければ知ることができなかったルワンダの感情的クライシスへの対応に触れることができ、参加してよかったと思います。 他者に病名をつけられるのではなく本人の言葉で痛み、問題に名前をつけること、そこに一緒に寄り添っていくことのもつ力強さに感動しました。 問題が問題であるということ、どんな場面、相手であってもその人の背景、生活している文化、環境などにも意識を向けていきたいと思いました。 |
| とても言葉を大切にされていること、周りからつけられた言葉ではなく、その人の言葉で、その人の心の中を表現してもらうことが心に残りました。 パンデミックの中どうすればいいかは当事者たちが教えてくれたという場面に当事者たちの強みを見ることができたし、それを受け入れ実践していったことに相手を尊重するところを感じました。 マハロへの手紙の場面では、自分はマハロです。これは自分への手紙なので送って欲しいという反響の場面では、涙が込み上げてきました。手紙を書くという効果について以前に触れる機会があったことを思い出しました。 言葉を大切にする、その人の中にあるものを大切にする、相手を信じ、こちらの考えを押し付けたり操作したりしないようにしたいと思いました。 |
| 貴重なケースの紹介は、再現して頂きありがとうございました。 語ること自体しんどい問題こそ、ナラティヴ・アプローチということを、ルワンダのジェノサイド環境での生存者支援という実践から、見せていただいたと思っています。 素直に、感動しました。 最初のアプローチから「問題の名づけ」というプロセスで、「石」「牛」「血」「太陽」など、ルワンダの大地や土埃り、陽射しが五感を通じてイメージできるような表現が随所にきかれ、そこに居る方たちの等身大の表現で、問題が外に出てくるプロセスが、体感できました。そして、それらが、自分だけでなく同じ痛みを持つ誰かとつながっていったとき、さらに、その問題に向き合う存在が力強く、そしてより一層、美しく響いていくことに心が震えました。マハロの手紙では、思いがけず泣いている自分がいました。そして、それがさらに「詩」として昇華されていくかのごとく、多くの人を支えるメロディーとしてパンデミックというブロックをものともせず、ネットやTVを介し時空を超えて、波及していく光景を想像すると、さらに身体が震えるようでした。 想定外の理不尽な災難に押しつぶされたとき、「がんばろう○○!」と励まし合うだけでなく、「踊りながら泣ける場所に行こう!」ということを声高に言えるような、支援が日本でもできたらと、カウンセラーの端くれとして思いました。 また、私自身、マスコミで記者のキャリアを持っているけど、どうやって今のカウンセリングと結びけたらいいのか、自分の中で分離させてままでいたのですが、今回は何か大きなヒントをもらったような気もします。 こうした、機会を頂けたことに感謝します。 |
| プログラム 1-4:日精研動画カーニバル |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 昨日、たまたまナラティブの講義を受けました。今日はナラティブのデモを見れて、理論とデモが繋がって、理解が進みました。 |
| 貴重なビデオが拝聴出来てうれしいです。どれも魅力的で、時間が足りないくらいでした。 これだけの素晴らしい教材がもっと多くの方に届けられたらいいと思います。 |
| 日精研さんの各種ビデオアーカイブは、ナラティヴ以外の心理療法を知る上で非常に有効な方法だと感じました。 |
| プログラム 1-5:まるごと性別解体ショー2025 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 今回は2021年に出版された「性別解体新書」の内容に沿ったお話が多かったと思いました。本を読んだだけでは十分に理解できていなかったことが多々あり、改めて学ぶことが多かったように思います。今回の講演及び「性別解体新書」で目指したことは何だろうと考えたとき、私の解釈では「自分で自分を好きになれる」ではないかと思いました。 |
| 大変興味深くお聞きしました! 「性自認」、「性別違和」という感覚(概念)について、長年捉えきれなさがありました(自分のことについても、お話を聴かせていただいた方の体験についても)。 どうも本質的なもののようにしか捉えきれない感が拭えずにいたのですが、それも、社会文化的に構成された側面がある(性他認なんだ)ということをお聴きできて、そう考えていていいんだなと思えました。それに伴って、「こころにしっくりくる性」という表現もありがたくて、同じような文化にさらされていても、「しっくりきますか?」という問いへの応答や表現の個別性はどのような場面でもあるなあと思えました。 それから、「好き」の多様性のことも、日ごろからモヤモヤ考えていたことを言葉にしていただいたような気持ちでお聞きしました。 誰とどのような関係を結びたいか、ということは、自分と相手との間で様々に持っておいて良くて、おっしゃっていくださったように、自分が入れる既定の名前や箱を探すのではなく、自分でそれをなんと呼びたいか考えていいし、名付けていいものとして考えていきたいと思いました。 |
| 6月3日FLATでの国重さん&奥野さんに続き、今回の企画でアイデンティティに関する理解が深まりました。ゴフマンの「行為と演技」、役割取得がアイデンティティに繋がるというところ、「ある」から「する」への転換などが興味深く感じられ、アイデンティティについてもう少し探求したくなりました。後半での「身体の性別」、「心の性別」、「性的志向」を分けるなど、非常に納得感の高い内容でした。資料を頂けなかったことが残念です。 |
| 昨年もこのプログラムに参加しました。今年は内容が更に濃くなっていて、セクシュアリティについての言説の深さ、そして、それによる誤解、またそれを覆す新論に、何度も目の鱗がはがされたようでした。智美さんの語りは、楽しく、優しく、あっという間の2時間半でした。また、今回は智美さんが理事をされているNPOシーンの会場とカーニバルのZoom参加者をつなぐという初形式でした。シーン会場の方の声も聞くことができ、広い関係の中で共に話を聞けた感じがしました。こんな形式も楽しいなと思いました。このような深く楽しい内容をチャリティーで話してくださったことに感謝します。次回もぜひお話を聞きたいと思います。 |
| プログラム 2-1:今改めて考える対話の可能性〜武器を取った若者たちから学んだこと〜 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 世界の平和に向けてこのように取り組んでおられる方がいる事に、勇気をもらった。 |
| アクセプトインターナショナルの人たちとは対面で会って寄付もしましたが、今回本格的に活動を知ることができて、より理解と共感が深まりました。私の実践も障害者へのリハビリですが、同時に社会の偏見にも関心を向けています。わかり会えなさを超える、危うきに近寄る、諦めない支援は本当に絶望的な状態を変える力があります。力をもらいました。 |
| 今まで自分が避けてきた分野に触れることができた機会でした。「外国人は全員敵だ。でもこの日本人は違う。」と言われるよう危険な環境でも愛を持って善意の姿勢で接している方々に驚きました。そしてその姿勢は私の身近な支援の場でも共通すると感じました。「共に憎しみの連鎖をほどいていく」とはどんなことか、また自分にできることは何かを考えていきたいです。 |
| 永井代表のお話を伺って驚きと感銘を受け、もっと知りたいと思っていましたので待望のプログラムでした。今まで知らなかった実状に目を開くことが出来、命を懸けての実践に真に信じられる「人」の崇高さと勇気を実感しています。 |
| 先日の代表・永井さんのお話に引き続き、広報の山崎さんのお話もうかがえて、繰り返し聞くことにより、大事にしていることが明確になる気がしました。強く印象に残ったのは、午前中の藤田さんのセッションとも響き合うことですが、支援する時にお互いを「普通の人」ととらえ、ともに生きていく姿勢でいることです。支援者として自分もそうありたいと考えていますが、危険な現場で時には脅されることもあるような環境で「普通」を貫くのは並大抵のことではできません。何が山崎さんを動かしているのかを考えると、「できる・できない」ではなく、自分事として「やる・やらない」の問題ととらえなおし、行動していることが大きいのではないかと思います。 コミュニティで生きていくことを前提に、その場に置かれて「役割」を果たすことができたら、その人は以前とは別人になるというアイデンティティの流動性、相手の価値観を聴くところまでいけば対話ができるということなど、ナラティヴ・アプローチとの共通性には驚きますが、アクセプト・インターナショナルの方々が、まずは実践ありきであり、理論は後と言っていることも信頼できる気がします。「あきらめない」という姿勢を大事にしていきたいと思います。 |
| 遠く離れたソマリアの人々を長年支援されていることは並大抵な忍耐と思いがないとできないだろうと思いました。また、思いだけでなく命の危険を賭してまで現地に行かれていること。また、その結果、外国人は敵とみなされる地域の現状の中で、「この日本人は大丈夫」と信頼を得るまでになられたこと、本当に驚くばかりです。早速、アクセプト・アンバサダーに申し込みました。 |
| アクセプトインターナショナルさんの活動は、えぬぱっくに関わることがなければ知らなかった活動でした。代表の永井さんのお話も以前聞かせていただき、大変衝撃を受けました。 今回山崎さんからは更に、対話の生成について学ばせていただけたように感じています。 同じ20歳前後の若者であること、環境によって選ばざるをえなかったこと、知らないことばかりで恥ずかしくなりました。 受け容れられること、希望を真剣に示されることで変わっていけるということ、 希望を作り出す活動であるということ 学ぶことが大きく、私自身の仕事にも自分の生き方にも参考にさせていただきたいです。 先ずはこの活動を知ることができたこと、この場をひらいて下さったことに感謝したいと思いました。 |
| プログラム 2-2:発達特性を持つ人に対話がなぜ有効か |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 障害特性は治る(気にならなくなる)、と断言するとらっちさんの言葉は、ずっと心に残ると思います。そんな対話を根気よく続けていけたらなあ、と思いました。時間枠を超えてからの質問やお話に皆さんで言葉を交わせたこともとてもありがたかったです。久々のナラティブ界隈、心地良い空間と時間でした。ありがとうございました。 |
| プログラム 2-3:もしもマイケル・ホワイトが大阪のおっちゃんだったら?! ~マイケル逐語録 大阪弁上演会~ |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| とてもおもろい時間を一緒に過ごさせていただき感謝申し上げます。 大阪弁での上演は、逐語がダイナミックで臨場感あふれて動き出し、お互いを巻き込みながら新しく立ち現れてくる場を体験できたように感じました。自分でも逐語を読んでみると、自分なりのニュアンスを大阪弁だとこういう風に言うだろうなという感覚を、自分が持っていたことに若干の驚きと納得を感じつつ、お互いに伝えあうことを大切にしている文化なのかなと少しだけ感じ取れたように思いました。厳しいこと言っても、「知らんけど」と最後にぽそっと言うことのやさしさも感じました。ほかの言葉でも聴いてみたくなっています。ありがとうございました。 |
| 「おもろい」という感覚や楽しむ(プレイフル)ことの大切さを改めて感じました。言葉は文化であり、ローカルさが持つ身近さや親密な雰囲気は、その土地で話すときに重要になってくることも考えました。 |
| とても面白かったです。遊び心満載でした。ただそれだけではなく、言葉についてたくさんの気づきをいただきました。書籍が標準語で訳されることの効果や、方言の持つ影響などについても考える良い機会になりました。 |
| プログラム 2-4:組織で対話をはじめるファシリテーターの奮闘物語 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 午前中に参加したオープンダイアローグでリフレクティングを体験していたので、お話がとても腑に落ちました。 |
| ナラティブが個人だけでなく組織にも応用できること、またRCの活用を聞き刺激になりました。ありがとうございました。 |
| 組織に「対話」の場を作る際に、対話を単なる手法として扱わない、という言葉が耳に残りました。 多様性を認め尊重し合いながら、その職場で働き続けられるようにするために対話が必要なんですね。 紹介いただいたケースからは、RCがマネージャーさん達にとってのある種の癒しの場にもなっているように聞こえました。 |
| 参加してよかったです。ありがとうございました。 端的に必要なポイントを押さえた資料と説明、具体的な事例などとてもイメージしやすく、とても得るものの多い時間となりました。ありがとうございました。 本日頂いた資料を読み返し深め、今後に役立てて行きたいと存じます。 |
| お二人が時間をかけて準備してくださったことが質、量ともに容易に理解できる内容でした。カーニバルでこの内容をわたしたちに共有してくださったことに感謝します。ありがとうございました。 まもさんが紹介してくださった方のことは全く知りませんでしたが、考え方として整理してくださって、理解を助けてもらいました。 くにさんの現場のお話は興味深く、ファシリテーターとして実践を重ねてきたくにさんだからこその信頼を土台に実施されたRCの報告はわたしもこのような実践ができたら・・・と心が動きました。 |
| RCを、組織開発に広げて応用するという発想、そして、それを実際に行動に移し企業に適用していることに、大きな可能性と期待を感じました。また、その方法も顧客の人たち(クライエント)に選んでもらうというその姿勢もナラティヴらしいと思いました。ありがとうございました。 |
| RCのことをもっと詳しく知りたいと思いました。 |
| 個人カウンセリングでも、組織開発でも、対象者がAuthentic(本気で)取り組むことができるかという部分に、支援側は何ができるのかが問われているとあらためて実感しました。「~したらうまくいく」といった前例踏襲が効かない不確定時代の中で、支援者も含めみんなが、レジリエンスやネガティヴケイパビリティーなど、「オリジナリティーを創造する粘り」が必要だとあらためて思いました。その挑戦に、Reflective ConversationやNarrative approachの姿勢や構造が大きな支えになると再確認させてもらいました。私自身も、外部企業支援者として、従業員さんの事業プロジェクトやキャリアなどの振り返りミーティング・研修等の場などで、RCを取り入れ始めています。どこかで同じように実践者の仲間がいてくれることに勇気を頂き、さらなる研鑽へ励みを頂きました。ありがとうございました。 |
| 利益や成果が優先される企業という枠組みの中で、対話を持ち込むなんて難しいと言って何もしないでいるのか、それでも時間と労力をかけて難しさがわかりながらもやってみるのか、それを何が分けるのだろうと考えたときに、その一歩を踏み出すきっかけとなる何かに触れてみたくなりました。 |
| 会社勤めの管理職の方と社外の私との1on1セッションで聞こえてくる管理職の方の意見と同じような意見がアンケートの内容にあったので、今の上層部や管理職の方が対話について体験して学ぶことはとても大切なことだと感じました。 |
| プログラム 2-5:ふだん遣いのナラティヴ・セラピーの探求 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| ナラティブとのふれあい方、付き合い方の実践例がうかがえて参考になった |
| カウンセリングの場だけなく、普段の生活のなかでもナラティヴを使えると良いな、と思いました。 |
| まずは日常からナラティヴセラピー視点で眺めていくことでしょうか? |
| 普段の語りにもっとナラティブの外在化を意識してみようと思えたこと |
| 相手に問いかける時に「何で?」を「何が?」に変えるだけで、話のニュアンスが変わってくるという例は、ぜひ日常の取り入れたいと思いました。また、ゲストの方のそれぞれのナラティブへの関わりが、とても興味深く、また、とても身近に感じました。様々なヒントをいただき有り難かったです。 |
| プログラムに参加して、ナラティヴセラピーがより身近に感じられました。居心地よく参加させていただきました。 |
| プログラム 3-1:フーコーを読んでみたい |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| ナラティヴセラピーとフーコーとのつながりに気づかせていただける機会となりました。ありがとうございました。 支援者としては、統治する側の意図や狙いと、統治される(特にその枠組みをいろいろな事情があってはみだしてしまう方々)側の事情を知り、その間をとりもっていく役目を積極的に担っていきたいと、改めて思いました。 |
| このプログラムを通じて、克貴さんがフーコー「推し」のお立場で、数ある著作の中から「かっこいい」「しびれる」「アツい」と感じられた部分を抽出して、初心者にも受け取りやすい形で結晶化させて提供してくださったことに感謝します。 私は、フーコーの本(解説的な本等も含め)を一冊も読んだことはなく、今回のプログラムがなければ、一生出会えなかったかもしれないフーコーのメッセージや考え方のエッセンスに触れさせて頂けたことは、とても幸運であると感じました。 特に、後半の「批判的検討の重要性」のパートは、自分が日々感じていること(=組織の中で仕事をしていく上で「権威」や「自明」とされるアレコレへの思いや、国内外で起きている厳しい、危うい状況等への思い)について、「励まされる」ような感じがしました。 とても興味深く拝聴しました。貴重な機会を提供くださり、ありがとうございました。 あと、2日間にわたりお昼に提供された「リフレッシュ・ストレッチ」や2日目朝の「ラジオ体操」も楽しく参加させて頂きました。ありがとうございました。 今回初めて「ナラティヴ・カーニバル」に参加させて頂きましたが、この土日にやらなければならないタスクが複数あったこともあり、参加したプログラムは上記3つだけです(あと、北大路書房さんで本2冊購入しました~)が、とてもたのしく、有意義な時間でした。 カーニバルの企画・運営に携わられた全てのみなさまへ、感謝をお伝えしたいです。 ありがとうございました!! |
| 克貴さんのやわらかな語り口のおかげで、フーコーのかっこよさが伝わってきました。個人的にはフーコーが体のことについて言っていることについて興味がわきました。 |
| プログラム 3-2:”協働のためのアサーション”にちょっとだけ触れてみるツアー |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 大変良かったです。 |
| 対人関係の中で、また集団の中での対話場面で、自他を尊重するには、アサーティヴな表現が有効になると思いました。 |
| ・アサーションの3つの表現についての復習となる時間になりました。 ・事例についてのワークでの事例をどう捉えるのかという対話が出来たことがよかったです。その中では、アサーションにおいても他者理解が大切であることを感じました。 |
| 対話を通じて学びを深めることができました。 ありがとうございました。 |
| 文字だけでは分からない口調や、相手との関係性によるということが実際の場面の再現で良く伝わりました。様々な条件によって、攻撃的になったりアサーティヴになったりということもあり、一概にはいえないからこそ、コミュニケーションの仕方への心配りが大切だと思いました。 |
| I amOK.You’re ok.を大切にしたいと思いました。つい、自分が頑張ればいい…みたいな考えになることがあります。自分も人も大事にすることで協働が成立するといいなと思います。 グループワークで話すことで色んな気づきがありました。ありがたかったです。 |
| アサーションについての基本的な知識はありましたが、今回のプログラムに参加して、ずっと深く、広がりのある概念であることが理解できたように思います。 |
| 自他尊重のコミュニケーションを、自分の中でも意識していきたい。と、思いました。 |
| プログラム 3-3:レジェンドらが読んだかもしれないクラシックな本 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| あらやすさんの頭の中を少し覗くことができて、楽しい時間でした。さまざまな思想家の相互関係とナラティヴ・セラピーへの影響など、通常、語られている以上のリンクを見せていただきました。 |
| ブーバーの「我と汝」は20代に購入し40年以上積んであった本です。プログラムを見た時にブーバーの名前を見て、ブーバーなんだと驚きました。改めて眺めてみたい(とても読むなんて言えません)と思います。このような機会をいただいてありがとうございます。 |
| 「ナラティヴの源流は一つではない」そのことについて、様々な理論家実践家をご紹介いただき、背景まで聞かせていただいたことはとても興味深かったです。時間がいくらあっても足りません。もっとお話を聞いていたかったです。 |
| 「問題を外在化することで輪郭がはっきりしてくる」まではなんとなく自分の中で理解していたように思っていましたが、名づけることで問題自体が「それ」から「汝」になる。そのことは問題にも「やさしい光をあてる」ことで、他の入れ替えることのできない大切なものとしてもう一度自分に迎え入れるのが外在化なのかなと、新たな視点をもらった気がしています。システム世界に浸食されていく生活世界と区別すること自体もシステム世界の仕業なのかな、そんなことも思ったりしました。カレーの話は面白かったです。そこは組織の話に紐づけてもう少し聴いてみたい気がしています。 |
| 色々な方のお名前が出てきて、それぞれの方の考え方などの似ているところや違いなどを知ることができて楽しかったです。できればもっと時間をかけてゆっくり詳しくお聞きしたいと思いました。 |
| プログラム 3-4:日本文化を考え、自分の信念・価値観をアップデートしてみる |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 日本文化が形成されてきた背景、欧米との差異がよく分かりました。リベラルに日本文化が及ぼす影響を考える機会になりました |
| 改めて日本人になった自分のことを振り返って、あまり幸せと感じない日常について これからはポジティブに変換できるように心にとめておきたくなりました。 |
| アンコンシャスバイアス、固定概念やステレオタイプ等については、最近よく気にしている概念であったので、整理ができたように感じました。 日本人はという考え自体もステレオタイプにならないように、でもこんな背景があることがそこにつながっているよなという感じで、わかりやすく説明いただきありがとうございました。 あと、あらためて、「信念・価値観」と「支配的なディスコース」の関係を再確認し理解が少し進んだ気がします。 あと、相対化の方法でリフレーミングとブレインストーミングを使うのは、難しかったです。(これはおかしいよな、ということを考えるときに、リフレーミングでとらえなおすという手法では言葉にならず、何を言えばいいかわかりませんでした) |
| 先入観と聞くと悪いイメージがあるけれど、自分が大事にしている価値観もそれを相手に向けた時には一つの先入観になってしまう。ナラティブの可能性を探るという視点は、普段無意識にジャッジメントしている自分に、それ以外の見方があるよねと行為を持って教えてくれるものだと思った。また日本文化のキーワード「委ねる」と西洋文化の「構築」も感覚としてしっくりきた。小倉さんがテレビを見ている時も思考の柔軟体操をしていると聞いて、私も「こうだったらどうなんだろう?」「こう考えることもできるのではないか」と体操をしながら聞くことを取り入れてみようと思います。 |
| 自分を含めた人々の信念価値観は 生まれた時は真っ白だったものが 生まれ育った文化や風習 環境に影響を受けて 何の疑問も持たず本人が気が付いていない事が厄介で そんな信念価値観によって文化や環境に与える影響が大きいという コレが当たり前 常識だとされている世の中の無理解によっても 本当に何度も傷付けられましたが 韓国では器を持って食べるとお行儀が悪いという事から 所変われば何が常識で当たり前かも変わってしまう事から 常識や当たり前という考え方に疑問を持つ様になりました ひとりひとりが自分の固定観念に気が付き 更に信念価値観という支配的ディスコースに向き合い おかしな法律や制度までどんどんアップデートしていかなければ やはり今のままの文化や風習 環境に影響を受けての信念価値観が繰り返されてしまうと思いながらお話しを聞かせて頂きました 様々な信念価値観を受け入れる豊かさがあれば 誰もが自分自身のナラティブ=人生の物語を尊重されて その人らしく生きられる様に 法律や制度まで変えなければ 本当の実現にはならないと思います |
| プログラム 3-5:能登半島地震・豪雨の緊急支援活動 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 地震・豪雨災害から時間の経過とともにどこか他人事になっていきつつあった事が、3人の皆様の支援の報告をお伺いして胸にこみ上げてくるものがあり、今も被災地の皆さんは目の前の問題に時に圧倒されたり悩み葛藤しながら踏ん張って生活していらっしゃるんだなと感じることができました。そして、片道7~8時間かけて支援に向かわれたそのエネルギーに驚き、私自身そんな熱い気持ちで行動できてるのかと自問自答せずにはいられませんでした。また、皆さんがセルフケアの一つにRCを挙げてくださり、支えになられていた様子を聴いて、RCの広がりと可能性を改めて味わいました。私もその一人になれるよう頑張らなければとエネルギーをいただきました。ありがとうございました。 |
| 「役に立ちたい」と思う気持ちを、そのときの状況に適応しながら、そして被災者へのケア倫理を繊細に意識しながらも、まずは飛び込んで「行動化」されたエネルギーに感銘をうけました。 廃材を燃やす銭湯屋さんの「家の弔い」という言葉や、自然の中で自主避難所手作り運営されている住民の方々が「ここは○○リゾート開発よ」と名付けたりしているエピソードを聴かせて頂き、被災者の方々の心痛と力強さを両方受け取った気がしています。その声を大切に聴きとり、拾い上げ大事することこそが、支援なのだとあらためて実感させられました。 そのために、最初はよそ者でも、「もううちの職員よ」と言われたり、「お誘いを受けるような関係」になる、プロセスや働きかけ、姿勢は、オリジナリティーは各々の個性であり覚悟でもあることもあらためて受け取った気がします。 |
| カウンセラーの方が、片道何時間もかけて、たいへんな思いをしながらも、被災地の学校へ支援に入られたというお話を伺って、とてもありがたく思いました。また、スクールカウンセラーの活動指針の第一番目に「先生方を支える支援活動を」という項目があったと聞いて、とても驚きました。何よりも児童・生徒の支援が最優先であって、「生徒を支援する立場である教員への支援の優先順位は低い」と思っていたからです。また、支援に入られたカウンセラーの方々を安心の中で支える場やRCのようなしくみもあったと伺いました。教員もカウンセラーも対人援助職ですが、あるときは支え、あるときは自らも支えられるようなしくみが確かにあるということの尊さを思いました。 |
| 大切なお話を聴かせていただき、ありがとうございました。 どうしようもない現状が目の前にあり、限られた時間や制限のある環境の中で支援職として一体何ができるのか?を突き付けられる状況での取り組みや経験を聞かせていただいたんだと受け取っています。それは支援職としてでもあるかもしれないけど、人として何ができるのか?でもあり、何ができるかではなく、人としてその場にどのようにいれるのか?のお話でもあったことがとても印象に残っています。 支援するってなんだろう?考えてしまいました。人によっても違うし、職種によっても違う。様々な違いがあるからこそ難しいことも生まれるけど、よさもきっとあるのだなと思いました。考え続けることが大切なのだと改めて思うことができました。 また、「活動は一人ではできない。でも、ひとりでもがんばる覚悟は持っていたい」の言葉。 私もそうありたいと改めて強く思わされました。 まだまだ、お話が聞いてみたかったです。 ありがとうございました! |
| プログラム 4-1:希少・遺伝性疾患を抱える人へのナラティヴ・アプローチ:海外の実践から日本での可能性について考える |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 感想も言いましたが、辛い人に寄り添える人で有りたいと思っています。遺伝カウンセラーがそういう人たちなんだなと言うことがわかって嬉しかったです。 |
| 遺伝カウンセリングについて知ることができて良かった。診断に伴う驚きや疑問に寄り添う場面の大切さに想いを馳せました。 |
| 遺伝子のカウンセラーという存在を今回初めて知りました。 遺伝子のことなど専門知識と必要で大変なお仕事だと思いますが、本当に大事なお仕事だと思います。 |
| 遺伝情報は、一度知ったら後戻りできない、ということが特に印象に残りました。しかも、自分だけではなく、親など複数の人の個人情報ともかかわるということでした。本人に対して、そして家族等に対して情報をどう扱うのかが専門性としても倫理的にも重大なことだと思いました。なお、「後戻りできない」ということから、LGBTQにおけるカミングアウトを連想しました。こちらも一度、他者が知ってしまったら「聞かなかったことにしてください」と言っても通用しません。まったく同じではありませんが、情報の扱い方がますます重要になってくるなぁと思いました。 |
| タイトルを見たときには、遺伝子というある意味非常に科学的で決定論的な世界とディスコースへの対抗という側面のあるナラティヴ・セラピーはかなりの距離があるような印象を持ちました。しかし、かなり決定論的な診断結果だからこそ、それをどういう意味として受け取るのか、というところでナラティヴ・セラピーの重要性があることがわかりました。こうした活動がもっと広がるといいと思いました。 |
| プログラム 4-2:音楽療法を通して出会った経験 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 音楽療法での本当に貴重な事例やご経験をお話しいただき、音楽と言葉のツールの違いはあっても、人と向き合う、人とつながるという事をどうとらえるかの大切さを考える機会となりました。 本当にこの機会でなければ聞くことのできないお話しばかりを、たくさん聴かせていたらいたように感じます。 音楽と発達、教育との関係性の一端を垣間見させていただき、さらに勉強したいことが増えました。 また、音楽療法ならではの現場の感覚、葛藤も目の当たりにし、揺れながら個々の人に向き合っていくんだなという事、またクライエントを取り巻く方々との関係や連携、組織へのかかわり方も、自分の周辺でも考えていきたいと思いました。 |
| 音を通じて、どのように人と関われるかつながれるかに興味が向きました。つい言葉や意味の世界に注目してしまいがちですが、それ以外の表現があること、その表現の背景にはメッセージがあることを考える機会となりました。 |
| 時間の都合があり最後までいられなかったのですが、大変貴重なお話を聞かせていただいて感謝しております。私自身が学生時代、音楽療法に興味を持っていたのですが、(仕事として)当時はいろいろな難しさがあり仕事としての実現は断念したという経緯があります。ながねん違うことをしてきましたが、やはり心理、人と関わる、音楽、というキーワードは変わらずにあったので、現場に出ておられ、たくさんの経験をお持ちの方にお話を伺えたことはとても気持ちに刺激をいただいたと思います。具体的に何ができるかは分かりませんが、また音楽療法の本を読んでみようかと思っているところです。また、同じような機会があったらぜひ参加させていただきたいと思っております。素晴らしい企画をありがとうございました。 |
| 音楽療法と言っても必ずしも音楽だけではなく クライアントの方の状況や感情 周りにいる方々の気持ちや状況など全てを汲んだ上での音楽を提供するもしないも含めた 音楽療法の大事さや重さ 寄り添い方などに思いを巡らせながらお話しを聴かせて頂きました クライアントだけなく周りの方々との「その時間」を大切にする関わりをお伝え頂けたと感じました |
| プログラム 4-3:ワーク「擬人化した問題さんにインタビュー シーズン2」 |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 悩み人をさせていただきました。問題さんになって考えることで、悩まされているだけの時には気付けないことに気付くことができたり、自分自身を見つめてみることができるという体験ができました。貴重な経験をさせていただきました。 |
| 問題さんを担当しました。 次は、話し手さんやインタビュアー役もやってみたいなと思いました。 外在化のプロセスを学ぶと同時に、自分にとっても良いトレーニングになりました。 貴重な機会をありがとうございました! |
| チャットにも書きましたが、改めて「外在化」について勉強してみたいと思いました。今は、特に、その構造についても興味があります。そもそも「外」って何だろう、どこにあるんだろうと。ありがとうございました。 |
| このタイトルにも外在化のヒントがあると思いました。「問題さん」と擬人化して呼びかけることから始めてみたいと思っています。ワークでは、悩み人を演じることや様々な角度から問いかけをもらうことで、いろいろな気づきがありましたが、まだまとまっていません。時間をかけて振り返ってみたいと思っています。 |
| 貴重な体験の場、ありがとうございました。 私は、今回の限られた時間と構成では、正直「擬人化した問題さん」脳になりきって、インタビュアーの質問自体をすぐに消化しきれない自分がいました。 一体一のカウンセリング時では、外在化して名付けるプロセスで、ゆっくりと「問題」と「自分」を分ける時間がもっていることを思い起こすと、逆に、そうした時間を持つことは重要なんだとあらためて確認させてもらった機会でもありました。 一方で、「擬人化した問題さん」の立場にたって、固定化した文脈にとらわれず、「問題さん」にもいろんなたくらみや意図があることを想像する「脳の筋トレ」にはなると思いました。そうした複数人でのトレーニングワークとして設定するときに、「どの程度(抽象化しすぎず具体化しすぎず?)の問題」を置くのかも大事なのだとも同時に実感しました。組織開発でも何を集団のissueとして置くかは、重要だということも、関連付けてその後、考えたりもしました。 ただ、やはりもう少し「問題さん像をキャラ付けする時間(名づけ)」を持たないと、きりかえが遅い私は、即、問題さんになりきれないこともわかりました。 お忙しい中、時間と労力をさいて、いろんな気づきを得られる機会をこの場を用意してくださり、感謝です。 |
| 支援者や相談者が問題を抱え込まないような活動をしていきたい |
| いつもの問題との関わり方から離れて客観的になれたのがよかった。グループワークで色んな方からお話しを聞けたことが興味深かったが、1人でもやってみても良いのかもしれない。…でも、それだとエンプティチェアみたいな感じになるのかな? |
| 問題さんの立場になってみて、問題さんが何を企んでいるのか、どういうところをポイントにして悩み人さんに入り込もうとしているのか、外材化することで視点が変わりました。問題さんとどのように対峙すると良いか、どのようにすれば退治できるか、関係性や距離の取り方についても考えるきっかけになりました。これからも、自身について悩むとき、また相談対応をするときに、外材化を試みたいと思います。 |
| プログラム 4-4:ボランティア体験を振り返る大学生のグループスーパービジョン RCを踏まえて |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 大学生がRCを取り組んだ時のことをつぶさに教えていただきました。大学生にとってもRCの構造は貢献できることを聞かせていただきました。RCの可能性がまた広がった感じがしました。 |
| RC にOWを取り入れてのスーパーヴィジョン。荒安さんの優しい、ゆっくりな語りの進行の中、学生が自分の体験を語り、リフレクトチームとの交互やり取りから、次第に深い語りに導かれていくプロセルを聞かせていただきました。自分のしたこと、しようとしたこと、これからやれそうなことが明確になっていきました。RCの可能性を強く感じました。 |
| 発表者さんのファシリテーターとしても問いかけがとても優しく、安心感があり、こんなことで言っていいかもしれないと感じさせる部分や普段の信頼関係があることで、学生さんそれぞれが感じた自分の考えや感覚などを正しい間違いという判断なしに表現できていたのではないかと思いました。グループスーパービジョンRCの可能性を見ました。 |
| プログラム 4-5:認証プラクティス |
| NPACCのホームページにも掲載していい |
| 認証という捉え方、考え方が具体的な例を通じて理解することが出来た。 |
| ステップ3の「自己認証」をやってみる、という試みが興味深かったです。認証をしてくれる他者がいるときばかりでなく、自分でもやってみることができる・・・という体験はとても記憶に残りました。自分に向けがちな厳しい眼差しをちょっと立ち止まって考えてみると、自分を大切にすること、大切にしようとしていることに気づける。大切な視点だと思います。このプログラムを大事に育てていけますよう願っています。 |
| 自分を認証するということに慣れていませんが、試みていくことは自己受容し大切にしていくことにつながり大切なことだと思いました。 自分のことも相手のことも敬意をもって大切に捉える姿勢を持ちたいと思います。 また賞賛ではなく認証するということや、会話の中で実践するにはトレーニングが必要だと思いました。 |
| 参加する前は、「認証」と言っても具体的にどのように取り組めばよいのかが分からなかったので、ステップごとに何をするのかを教えてもらえて、実践しやすくなったのが良かったです。他の参加者の皆さんも仰っていたのですが、自分で認証をするのと他者から認証されるのとでは受ける印象が異なるので(おそらく後者の方が受け入れやすい)、自分一人でワークに取り組むというよりかは、今回のように、あるいは友達と一対一でも、誰かと一緒に取り組むことが効果的なのかなと感じました。 私は今回、大きな悩み事ではなく自分の些細な行動を分析してみたのですが、「意図」を考える過程で、大きな悩み事にも通じる価値観の存在に気づきました。自分の中にその価値観があることには元から気づいていたのですが、日常の些細な行動にもそれが表れているということはあまり意識していなかったので、それに気づけて良かったです。 先ほど、誰かと一緒に取り組むことが効果的だと書いたのですが、こんなふうに自分一人で立ち止まって考えることでも新たな発見があるので、そういう時間を作ることが大切なのかもしれないとも思いました。 ただ、自分を「認証」しようと思うとやっぱりなかなか難しい部分もあって、わざとらしくならないようにするためにはどうしたら良いのか、試行錯誤する必要があるなと思いました(試行錯誤しなきゃって考えるのは、もしかしたらちょっとズレてしまっているのかもしれませんが……)。 |
| 自分で自分を認証するのはやってみてなかなか難しいものでしたが、 時間を取って、自分の中の他者と話して、できたことを認めていくという行為は喜ばしい時間でした。 また、他者からの認証をもらう機会もいくつかあったなかで、 受け入れるではなく、受け止めやすい表現の形だと改めて感じました。 あれでもないこれでもない会話や、可能性の一つとしての選択肢の提示があることで、 可動性の高い場や空間につながっていくんだと、希望をもらえた感じがします。 |
| 「認証」「プラクティス」その両方の言葉に惹かれて申し込みました。自分を認証する取り組みワークがあるとあまり理解せず参加していました。自分を認証することは、通常あまり意識しておらず、以外とむずかしさを感じました。行動のその意味を考える。無意識にやっていることや自分にとっては改めて考え直すほどでもないと当たり前になっていることにやはり何かがつながっていることが多そうだと思いました。行動だけ見ると「もっとこうしなきゃ」という思考に陥りますが、行動の意味を考えると別の側面から同じことを見やすくなるのだということも再度思えたように思います。ありがとうございました! |
| 最後の山口さん(参加者)の質問「認証が褒めるものになっていないかどうか。認証はその人がやっていることをそのまま認めることでは」が残っています。私自身、無意識に認証はその人の良いところを言葉にすると思ってしまっていたと気づかされました。もちろんそれも間違いではないのでしょうが、相手の意図をいくつかの視点できちんとお聞きして、それに対してそうなんですねという態度も認証であることは気づいていませんでした。と、ここまで書きながら認識が間違っていたらあれれ!?なんですが笑。 |